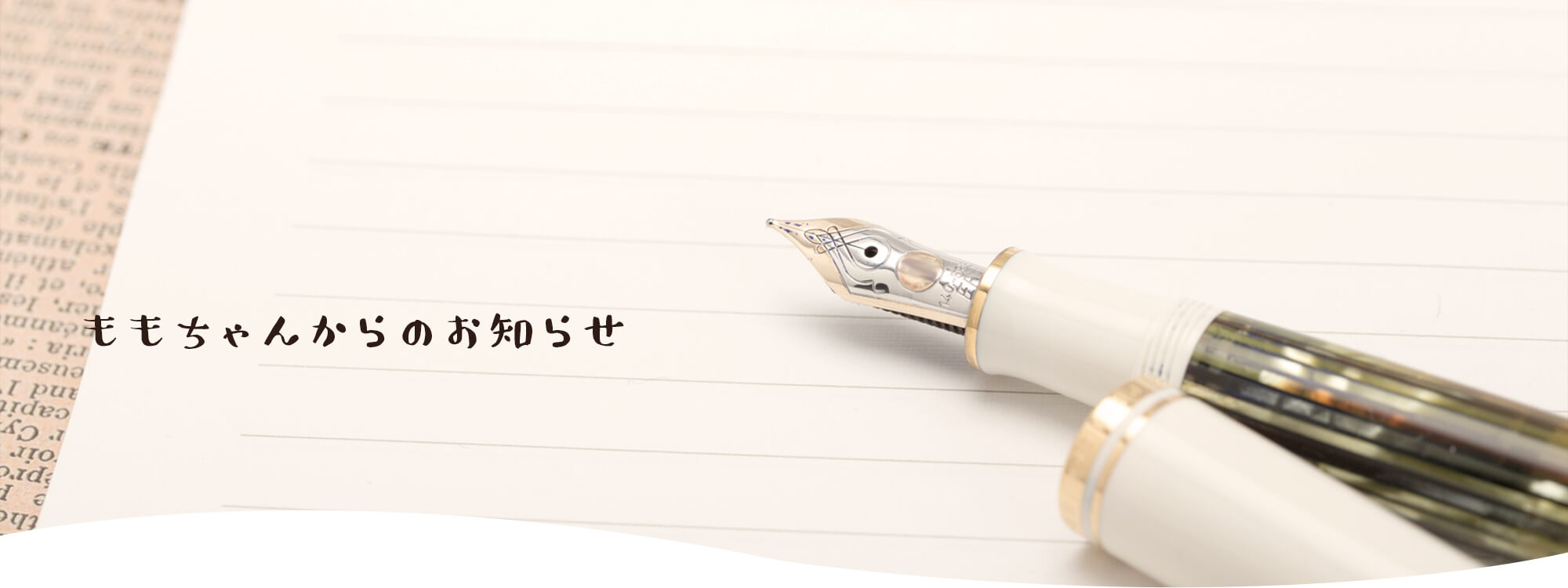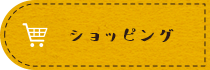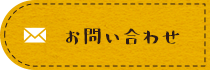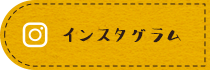皆さんこんにちは
株式会社米菓桃乃屋の更新担当の中西です。
~おせんべいの歴史と地域文化:日本人の“カリッ”という記憶 🍘⛩️~
1|「米菓」というカテゴリーの成り立ち
おせんべいは広義の「米菓(べいか)」に含まれ、煎(い)る・焼く・揚げるなどの加熱工程で米のデンプンを糊化→乾燥→再加熱し、香ばしさと歯ざわりを作る日本独自の食品文化です。奈良・平安期に寺社の供物として“焼き菓子”が登場、江戸期には醤油醸造の普及・米流通の安定化・街道の発達を追い風に、行楽と土産文化とともに一気に大衆化しました🚶♀️🧺。
2|関東と関西、二大系統の違い
同じ「せんべい」でも、東西で“噛みごたえ”に明確な違いが生まれました。
さらに、全国には多彩な“地の味”が存在。柿の種(新潟)や南部せんべい(岩手・青森)※小麦主体のものもあり、瓦せんべい(関西)など、地域の水・米・醤油・塩・海藻の違いが味の個性を育ててきました。
3|おせんべいと年中行事🎍
米は日本の祭事と不可分。ハレの日の贈答、法要の供物、地元祭りの縁起菓子としても役割を担ってきました。
4|おせんべい屋の系譜と“手焼き”の魅力
手焼きは、火と水分と時間の三角バランスを身体で覚えた職人芸。
-
生地の含水率で“膨らみ方”と“ヒビの走り方”が変化
-
焼き網の温度帯(強火の遠火/近火)で香ばしさの質が決まる
-
タレの糖度・粘度・塗布回数で「艶・照り・浸透」が変わる
ライブ感のある店頭手焼きは、香りで人を呼び込み、体験が記憶になってリピートを生みます。職人の所作は最高のマーケティング資産です✨
5|まとめ
おせんべいは“保存性の高い主食の化身”。歴史・行事・旅・土地の味が幾重にも折り重なった日本の食文化そのものです。現代のおせんべい屋は、この文脈を解きほぐして提供価値を再編集する「食文化の編集者」。次回は製造工程の科学へ。米粒がなぜ“カリッ”に変わるのか、現場で活きる理屈を紐解きます🧪🍘。