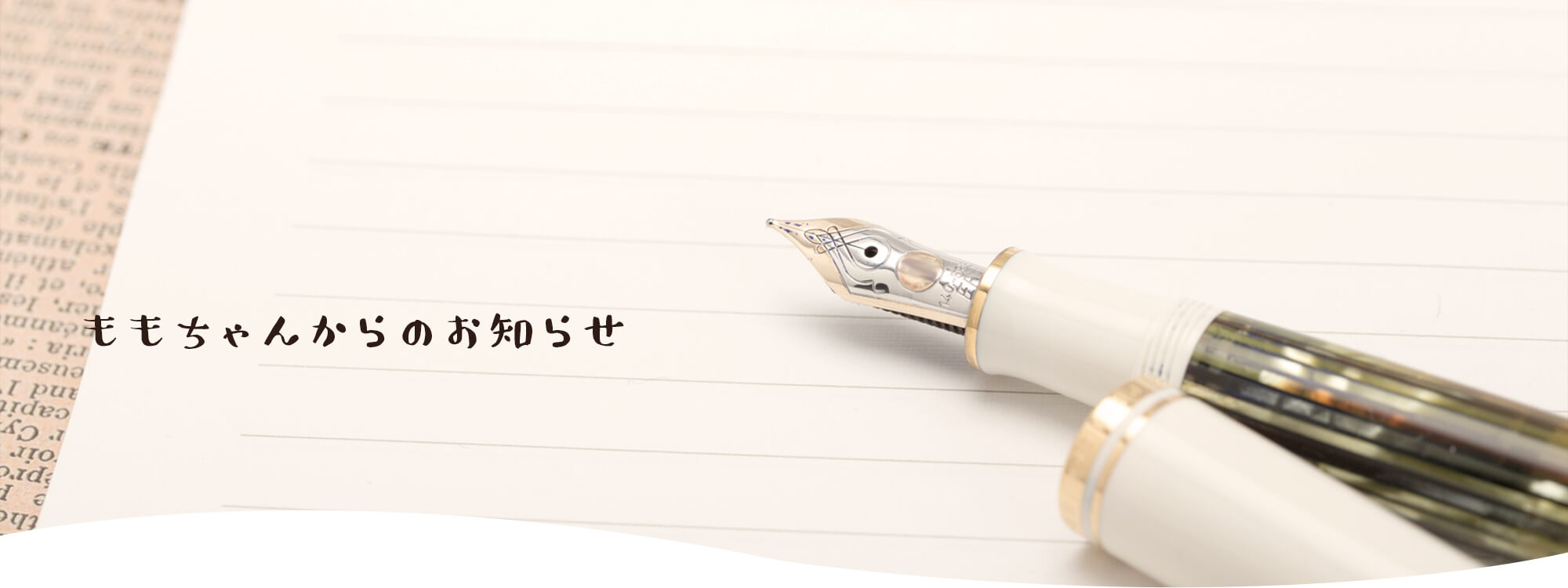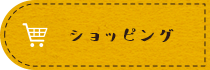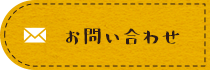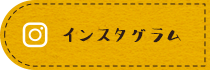皆さんこんにちは
株式会社米菓桃乃屋の更新担当の中西です。
~製法の科学:米と水と熱がつくる「カリッ&ホロッ」🧪🔥💧~
1|原料米の選定:食感の80%は米で決まる
-
うるち米:硬焼き・噛み応え重視。アミロース多め→パリッと割れ、歯切れ良い。
-
もち米:ソフト&膨化の伸びが良い。アミロペクチン主体→口溶け・香ばしさが華やぐ。
-
ブレンド比率:天候や新米/古米で吸水率が変わるため、目標水分(生地)を基準に逆算。
吸水と浸漬
米粒の中心まで水を入れる“浸漬”は、後工程の糊化と膨らみに直結。低温長時間で芯まで均一に。季節変動で吸水時間を見直すのが“歩留まりと均質化”の要です。
2|蒸し・製粉・成形:デンプンの糊化コントロール
-
蒸し:80〜100℃帯でデンプンが糊化→粘弾性が出る。ムラは割れ・欠けの原因。
-
製粉/臼引き:米の粒度で気泡の入り方が変化(粗め=ワイルドなヒビ、細かめ=均一で上品)。
-
成形:圧延厚みは“焼成時間・内部水分・割れパターン”を決める設計変数。薄焼き=高温短時間/厚焼き=中温長時間が基本。
3|乾燥:内部水分を“閉じ込めず、逃がし過ぎない”
焼成前乾燥の目標は表層サラッ、芯しっとり。
4|焼成:メイラード反応と褐変の設計🔥
香りと色は温度×時間×水分の三位一体。
5|タレ:糖度とアミノ酸のバランス
-
ベース:本醸造醤油+味醂・砂糖。**Brix(糖度)**で粘度を、窒素分で旨味を設計。
-
追い塗りの回数:1回=軽快、2回=照り強、3回=コク深。
-
塗布温度:生地温が高いほど浸透が進み、香り立ちが濃くなる。
6|トッピングと後がけオイルの科学
-
胡麻・青のり・七味:油脂分や精油が香りの“持続”を担う。
-
海苔:水分移行でしんなりしやすい→個包装 or 食べ切り設計。
-
後がけ米油/ごま油:0.2〜0.5%の微量で香り“跳ねる”。過多はベタつきの元。
7|品質・衛生:HACCP思考で“当たり前品質”を仕組み化
8|まとめ
「狙った食感と香り」は“米×水×熱×時間”の数式で再現可能。伝統の勘をデータで補助し、ぶれない看板商品を育てましょう。次回は商品開発&売場設計。小ロットでも利益を残すラインナップ戦略を解説します🧮✨。